【保存版】金は本当に安全資産?データで読むリスクと正しい付き合い方
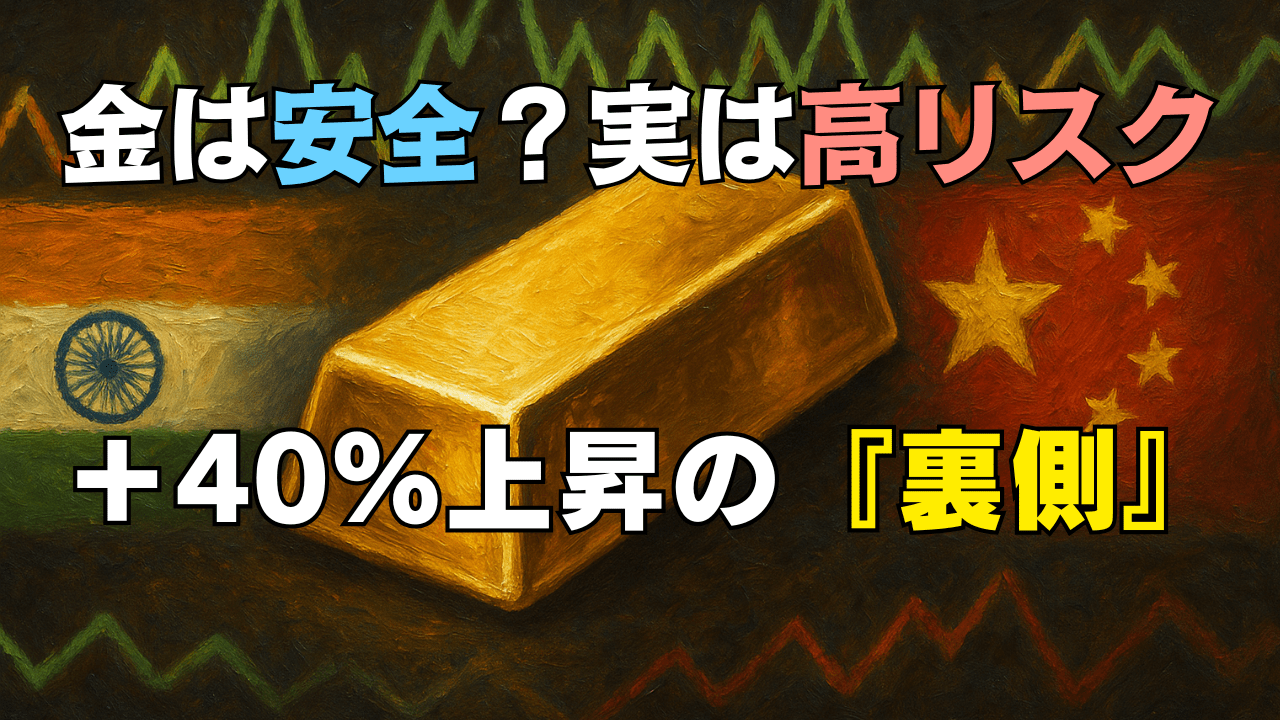
 しかし、『安全資産』のイメージがあるゴールドですが、その値動き(ボラティリティ)は決して小さくありません。株式や債券と比較しながら、金投資の本当のリスクや投資する際の注意点について解説していきます。
しかし、『安全資産』のイメージがあるゴールドですが、その値動き(ボラティリティ)は決して小さくありません。株式や債券と比較しながら、金投資の本当のリスクや投資する際の注意点について解説していきます。結論:金は『中〜高リスク資産』
金のボラティリティは、債券より明らかに高く、株式(S&P500)と同程度か、時期によってやや高いと言えます。したがって、実は『低リスク資産』とは言えません。◆直近3年の値動き(年率標準偏差)
・S&P500:15.80%
・金:13.53%
・米国債券:7.17%
※2025年7月時点のデータ。数値が大きいほど値動きが激しいことを示す。
直近ではS&P500の方がやや荒い展開でしたが、過去30年といった長期で見ると、金はS&P500よりもボラティリティが高いです。
では、なぜ金がポートフォリオに組み入れられるのでしょうか?その最大の理由は、株式との相関が低い(=違う値動きをしやすい)点が挙げられます。
株価が下落する局面で、金は相対的に強さを発揮することがあり、資産全体の値動きを安定させる『保険(ヘッジ)』ような役割が期待されます。
『金は暴落しにくい』は本当?
SNSでは、「インフレだから金は暴落しない」とか「供給量が限られているから…」「中央銀行が買っているから…」など、必要以上に強気な意見が目立つようになっています。しかし、これらは最近の金の構造的な強みの一面を捉えていますが、それだけを信じるのは危険です。
実際、歴史上で金は何度も急落を経験しています。
◆1980年〜1982年:約▲65%下落
→高インフレ退治のための急激な利上げ(ボルカー・ショック)。実質金利が上昇すると、金利を生まない金の魅力は薄れ、価格は急落しました。
◆1980年〜1999年:約20年間の長期低迷
→1980年のピークから、株式など他の資産への資金流入により、約20年にわたり価格が低迷。底値ではピーク時の約3割にまで下落しました。
◆2011年〜2015年:約▲45%下落
→金融緩和の縮小観測が浮上し、実質金利が上昇。インフレ懸念がくすぶる中でも、金は大きく値を下げました。
◆2013年:年間で▲28%のリターン
→わずか1年で3割近い下落を記録。特に4〜6月に売りが集中し、金といえども短期間で暴落し得ることを示しました。
◆2008年リーマン・2020年コロナショック
→流動性確保のための現金化局面では、金も短期で15〜25%程度の下げ。
まとめ:金は『守り』の資産ではなく『分散』の資産
金の価格は、インフレだけでなく実質金利、ドルの強弱、投資家の資金動向など、多くの要因で大きく変動します。歴史が示す通り、年間で▲40%を超えるようなドローダウン(高値からの下落率)は実際に起きています。
『暴落は考えにくい』と過信するのではなく、あくまで株式を中心としたポートフォリオのリスクを抑えるための一つのパーツとして活用するのが賢明です。
やはり金自体は成長せず、外的要因に大きく依存する資産です。バフェットが貴金属に投資をしない理由としても、この点を挙げています。
値動きが激しい方が積立投資に有利
『ボラティリティ(価格の振れ幅)が高い商品は、ドルコスト平均法での積立投資に向いている』とされています。その仕組みと、間違えると大損しかねない『落とし穴』を解説します。
なぜ『値動きが大きい』と有利になるのか?
ドルコスト平均法は、毎月一定額を投資し続ける手法です。この方法だと、価格が安いときには多くの量(口数)を、高いときには少ししか買わないことになります。結果として、平均購入単価を自然に引き下げる効果が期待できます。価格が大きく下落する局面があれば、そこで大量に仕込めるため、その後の価格回復時に大きなリターンを生む可能性があります。
これが『ボラティリティは積立の味方』言われる理由です。実際、シミュレーションにおいても、右肩上がりの相場より、大きな振れ幅を持って上がる方が、積み立て投資のパフォーマンスが良いことは証明されています。
◆(例)2万円を投資する場合
(価格が 100円 → 50円 → 100円 と動いた場合)
・一括投資:最初に2万円投資 → 200口購入 → 最終的に2万円のまま。
・積立投資:1万円で100円の時に100口、次の1万円で50円の時に200口購入 → 合計300口 → 最終的に3万円に。
ただし、どんな商品でも良いわけではない!【積立投資の大前提】
この『ボラティリティを味方につける』戦略が機能するには、絶対に外せない条件があります。❶長期的に上昇が期待できる資産であること
→世界経済の成長の恩恵を受ける広範な株式インデックスなどが代表例です。下落しても、いずれは回復・成長していくという信頼が土台になります。
❷価値がゼロになりにくいこと
→特定の個別株や狭いテーマのファンドは、最悪の場合価値がゼロになるリスクがあります。そうなると、いくら安く買い増しても意味がありません。
❸コストが低いこと
→信託報酬などの手数料が高いと、長期で続けるほどリターンが削られてしまいます。
⚠️S&P500とゴールドを組み合わせた商品(通称ゴルプラ)がありますが、信託手数料が高くなるので、長期投資には向いていません。
仮に0.1%程度の信託報酬の違いでも、月3万円を30年積み立てた場合、ゴール時には100万円以上(リターンに2%程度)の差が出ますから、なるべくならS&P500とゴールドは別々な商品に投資し、コストを抑えると良いでしょう。
【要注意】長期積立に絶対向かない商品
ボラティリティが高くても、以下の商品は仕組み上、長期の積立投資には適していません。◆レバレッジ型・インバース型ETF
→これらは日々の値動きの2倍や-1倍を目指す特殊な商品です。相場が上下を繰り返すと、『複利のマイナス効果』のような現象(ボラティリティ・ドラッグ)で基準価額が時間と共に減衰していく傾向があり、長期保有は絶対にNGです。
◆VIX指数先物などに連動する商品
→先物の乗り換え(ロールオーバー)に伴うコストが継続的に発生し、こちらも長期的に価格が右肩下がりになりやすい構造です。
まとめ:商品選びこそが積立投資の成否を分ける
ボラティリティの高さは、『長期的に成長する、低コストな資産』という条件を満たして初めて、積立投資の追い風となります。積立投資を成功させるポイントは、日々の値動きに一喜一憂せず続けること、そして何より最初に正しい投資対象を選ぶことに尽きます。
将来に備えてゴールド・米国株投資なら松井証券/PR
円安に備え、ドル建て資産は必須!松井証券は、為替手数料が往復(ドル⇄円)で無料なのが嬉しいです。たとえば、マネックス証券などは米ドルから日本円に両替する際は1ドルあたり25銭の手数料がかかります。つまり、松井証券以外だと1万ドル(約140万円)の両替に2,500円もかかってしまうことが。また、信託報酬手数料の低い『SBI・iシェアーズ・ゴールド』を選択できる数少ない会社なので、NISAでゴールド投資する場合も、ぜひ持っておきたい講座となります。
✔NISA口座は売買手数料無料
→しかも為替手数料でマネックス証券より2,500円(1万ドルあたり)お得
✔ボックスレートで一般口座も1日50万円まで無料
✔25歳以下なら一般講座でも株式取引手数料が無料
✔投資信託残高に応じた最大1%ポイント還元

私もNISAで米国株デビューしたのだ!手数料ゼロがうれしいのだ!
金はあと19年で枯渇する?【埋蔵量のカラクリ】
『金の可採埋蔵量は残りわずか!だから価格は上がり続ける』といった話をSNSで目にすることがあります。しかし、これは事実ではありませんので、こういった発言をしている人には警戒しましょう。
結論:『枯渇』の心配はほぼ不要。焦点は採掘コスト
『あと〇年でなくなる』という計算は、『埋蔵量 ÷ 年間生産量』で算出されます。しかし、この『埋蔵量』という言葉が誤解のとなっています。埋蔵量とは、実は可採埋蔵量(proven reserves)と呼ばれるもので、これは『現在の技術と価格で、経済的に採算が合うと判断された量』のこと。いわば『今掘れる場所として計算されている部分』にすぎません。
技術が進歩したり、金の価格が上昇したりすれば、これまで採算が合わなかった低品位の鉱床も『可採埋蔵量』に加わります。そのため、この数字は固定ではなく、状況によって変動するのです。
これは原油でも同様に騒がれていました。あと何年で原油は取れなくなるとマスコミが報じていましたが、価格の上昇と技術に進歩に伴い、埋蔵量が増え続け、今では枯渇するという人はいなくなりました。
金が『使ってもなくならない』原油と決定的に違う点
さらに、金には原油などのエネルギー資源とは全く異なる性質があります。❶地上在庫が圧倒的に多い
→人類がこれまでに採掘した金(約21.6万トン)のほとんどは、宝飾品や地金として失われることなく地上に存在しています。これは『地上在庫』と呼ばれ、新規の採掘量をはるかに上回る巨大な供給源です。
❷リサイクルが重要な供給源
→金の年間供給量のうち、約4分の1は古い宝飾品などを溶かして再利用する『リサイクル』で賄われています。価格が上がれば、人々は金を売りに出すため、リサイクル供給が増える傾向があります。
❸新規供給のインパクトが小さい
→そもそも、年間の鉱山生産量は、地上在庫のわずか1〜2%程度に過ぎません。実は新規供給が少し増減しても、全体の需給バランスを揺るがすほどのインパクトはないのです。
まとめ:『枯渇』よりも『需要』が価格を左右する
以上の理由から、金が物理的に『枯渇』して価格が異常に高騰する、というシナリオは現実的ではありません。金について考えるべきは『枯渇』といった供給サイドのリスクではなく、主要なプレイヤーである、各国の中央銀行の『需要動向』でしょう。
これまでも実質金利やドル相場、投資フローといった需要側のショックで大きな変動を繰り返してきましたから、要注意です。
もっとも、やはり長期で見れば通貨の価値は下がり続ける傾向が強いため、金価格は上がりやすいと言えます。無理なく日々積み立てながら、急落した場面では積み立て額を増やすと将来的に大きなリターンが狙えることでしょう。
史上最高値更新!インフレ加速中
金(ゴールド)に投資する場合は、非課税のNISA口座を利用して投資信託を購入するのが良いでしょう。◆金(ゴールド)
・SBI・iシェアーズ・ゴールド(信託報酬0.1838%程度)
・Smart-i ゴールドファンド(信託報酬0.275%程度)
・ゴールド・ファンド(信託報酬0.407%程度)
為替ヘッジありを選ぶと為替ヘッジコストがかかってしまいます。円安の継続性やコストを踏まえると『為替ヘッジなし』を選ぶのがベター。
また、松井証券は信託報酬手数料の低い『SBI・iシェアーズ・ゴールド』が選択できる数少ない証券会社の1つです。金投資の方法やポイントについては、以下の動画で解説しているのでぜひご覧ください⬇️
ブラウザ別の設定方法解説!✅口座開設前に必ず確認してください
もしCookieが無効で、プライベートorシークレットモード(黒い画面)を使っていると、トラッキングが無効になり、限定特典やキャンペーンを受けられなくなることがあります。夜だとダークモードでもアドレスバーが暗くなってしまうので、特にプライベートモード(Safari)・シークレットモード(Chrome)になってないか確認してください。
✅解決方法【Cookieを有効にし、シークレットモードを解除する】
口座開設前に、以下の手順で設定を確認し、バナーをクリックして手続きを進めてください!
🚨iPhoneからX(旧Twitter)アプリ経由でこのページを開いた方
まず、右下のSafariまたはChromeのマークをタップし、ブラウザでページを開いて設定を確認してください。
iPhoneの設定方法
Androidの設定方法
PC/タブレットの設定方法
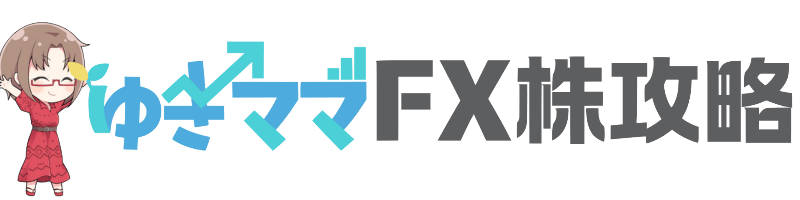







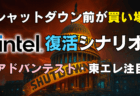
コメントするc⌒っ *・∀・)φ...オキガルニドウゾ!